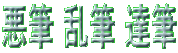
K-27
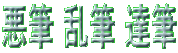
加 藤 良 一 2011年2月12日
総じて頭のよい人は字が下手だそうですが、果たして本当でしょうか。その逆もまた真かどうか知るよしもありませんが、そんな話は字がきれいな人からしてみれば聞き捨てならぬことかもしれません。では、頭のよくない人の字がきれいかといえば、もちろんそんなこともなく、当然下手な人もいます。
周囲を見回せば、友人で頭が切れるNさんの字はフタメと見られぬものですし、ときどきわけのわからないことを言い出すHさんの字がこれまた驚くほどきれいなんです。あれやこれや考え合わせると、なんとはなしに「頭のよい人は字が下手」説が妙に説得力を持ってくるんです。
因みに私の字はお世辞にもきれいとはいえません。こんな物言いをすると、暗に頭がよいと
下手な字のことを「悪筆」といいます。英語では“bad handwriting”。英語圏では昔から文章はタイプライターで打つんでしょうから、機械が打った字に下手も上手もありません。“handwriting”は、あくまで手で書く文字についてのことで、この点では日本と事情は同じです。
悪筆については「生来の悪筆」といわれるように「持って生まれたもの」との認識も世間には根強いと思いませんか。「持って生まれたもの」といえば、詩人で絵も描く星野富弘氏のことが思い出されます。氏は24歳のとき、事故で首から下が動かなくなってしまいました。それでも口にくわえた筆で何とか字を書くように挑戦したところ、慣れるに従って手で書いていたときの筆跡になっていったそうです。これは、字は手で書くのではなく、脳で書いている証拠になるのでしょうか。
ところで、悪筆とはすこしちがいますが「乱筆」というものもあります。乱筆とは、文字や文章を乱雑に書くこと、あるいは、乱雑に書かれた文字を指します。手紙の末尾に「乱筆乱文にて失礼いたします」とか「乱筆お許しください」などと、自分の筆跡をへりくだるときに使いますが、かならずしも悪筆を詫びているわけではなく、推敲も何もしていないことを詫びているんです。ですから、どう見てもきれいな字できちんと考えて書かれているのに「乱筆乱文にて失礼いたします」などと締めくくられると嫌味にもなりかねません。
一口に悪筆と言ってもつぎのようにいろいろなタイプがあります。
(一) 自分だけが読める字
(二) 他人も読める程度の字
(三) 他人が読めない字
(四) 自分も読めない字(?)
もちろん読めないとはいえ暗号とは一線を画しています。当たり前ですが、暗号は読めないことを目指しているのですから、そう簡単に読めては意味がないのです。また、「書」の心得のないふつうの人には読めなくても、専門家に読める字は悪筆とはいいません。念のため。
Wikipediaを見ると、石原慎太郎、黒岩重吾、田中小実昌、川上宗薫の四氏を「悪筆四天王」と呼ぶと書かれていました。石原慎太郎氏に至っては、あまりの読みにくさから印刷屋に「慎太郎係」という植字工がいたと
さて、悪筆はどうして生まれるのでしょうか。「生来の悪筆」とはいいながら、字を書き始めるのはけっこう年がいってからです。初めはお手本をなぞることから勉強し、次第にフリーハンドで書くようになっていくはずで、物を食べるように本能的に覚えるものではありません。
悪筆の原因には以下のようなことがあると思いますが、いかがでしょうか。
(一)単に不器用なだけ
(二)あるいは何らかの理由で指が思うように動かない
(三)線(文字)をどのように配置するかという二次元把握能力が低い
(四)基本ルールを無視した字、つまり癖が強すぎて読めない、書き順がまちがっているために読めない
(五)要するに何も考えない
などがありそうです。ただし、書き順がちがっていても文字として収まっていれば読むのになんら問題はありません。
基本ルール無視の例には、
(一)筆を止めなくてはいけないところを跳ねてしまう
(二)離さなければいけないところをくっつけてしまう、またはその逆
(三)そして線の長さの関係を無視する
(四)水平垂直斜めなどの角度をまちがう
(五)まっすぐでなければならないところを曲がりくねる
などが思いつきます。まちがった書き順で、あたかも草書のように続け書きなどされて困惑することがたまにあります。わかりやすい例を上げれば、ひらがなの「め」は「女」から派生したものですが、そのことを理解しているかどうかということです。
片や、巧みに文字や文章を書いたりすることを「達筆」といいます。「達筆をふるう」とか「達筆な人」とか、勢いのある筆使いをほめるときに用います。「あの人は達筆だ」は、“He writes a good hand.”あるいは“He has good handwriting.”というそうです。ほかに“skillful hand”という用語もあるようです。これはまさに書家の字といったあたりを指すのでしょうね。
星野富弘氏の例でも触れたように、誰しも「脳内文字」を持っているといわれていますが、ではどのようにして脳内文字は形成されるのでしょうか。
脳の中では、文字を書くたびに絶えず脳内文字を呼び出しては新たに上書きする作業を繰り返しているそうです。もともとはきれいな楷書からスタートしても、次第に自分特有の文字を何度も上書きしているあいだに、(よくいえば)筆跡に個性が表れるのです。いつも見慣れた自分流の文字ばかりを再インプットして上書きしていてはダメで、典型的で教科書的なつまり
書の基本に「臨書」といわれる学習法があります。臨書とは、先人の名跡をよく見て習うことで、学習の常道にして最も効果的なもの。また、ただ単に技法の習熟だけでなく鑑賞という側面も含まれているようです。子供のころにやった書道では必ずお手本を横に置いたものでした。
書家上田桑鳩氏は、臨書に対する姿勢としてつぎのように述べています。
「臨書の精神というものは、自分より優れたものに自己を無にしてかかって服従し、ひたすらに学習することから発すると思う。(…)この服従の精神は、やがてそこから自己の新面目が生まれ出る第一歩の手前であることを忘れてはならないのであって、この忠実な精神が、主観的な臨書に移っていき、手本とは形の違ったものをつくるまでついて回って、臨書を手本に連関させる重要な役目をなしているのである。」 (『墨』206号、2010年9・10月号より)
つまりは、臨書によって、名家の筆跡から自分の好む部分だけがわずかずつ骨身となって備わっていけば、古人に似たもののない書ができあがるということらしいです。こんなことに興味を持つようになったのは、ひとえにこのサイトに<書の世界>として、いろいろな書を紹介してくれている津田西山氏のお導きによるものです。
悪筆は音楽の世界にもあります。そう、楽譜です。たとえば、ベートーヴェンの自筆譜は汚いことで有名で、ぐちゃぐちゃと書きなぐったあとが生々しい。いかにも頭を掻き
またまたWikipediaからの引用ですが、指揮者の岩城宏之氏は、ベートーヴェンの<第九>のある箇所に疑問を抱き、自筆譜の写真版を調べたところ、出版社がフェルマータ(程よく伸ばす・拍を停止する)をディミヌエンド(だんだん弱く)と読みまちがったにちがいないと確信したといいます。自筆譜が読みにくい作曲家には、もう一人モーツァルトが有名だそうです。
私はまったく自筆譜に触れる機会などないのでよくはわかりませんが、シューベルトはアクセントとディミヌエンドが紛らわしいとはよく聞くことです。アクセントとはある音符の上か下に「>」のマークを書いて、その音を他より強調することですが、その「>」を横にもっと長く伸ばしたものがディミヌエンドですから、いい加減に書くとわけがわからなくなります。
そこへいくと、現代の作曲家多田武彦氏の自筆譜は、鉛筆と定規を使って丁寧に書かれていて、読みまちがいようがありません。実際、男声合唱プロジェクトYARO会に寄贈して頂いた男声四部合唱に編曲した『秩父音頭』の譜面は、あまりにきれいに書かれていたので、そのままで出版したほどです。
では、「脳内文字」は、どうすればきれいな字へと
一般的には、ペンを親指、人差し指、中指の3本が三角形になるようにして持ち、かつ指をゆったり伸ばした状態で持ちます。指が丸まって握り込むようになってしまうと、ペン先が自由に動けず、思うような形が作れません。まかり間違っても、赤ん坊のように手のひらで握りしめるような持ち方はやめましょう。以上のことは、右利きでも左利きでも原則同じことです。ときどき中指の代わりに薬指とか小指でペンを支える人を見受けますが、これで書いた字は推して知るべしです。
一つだけ今からでもできる矯正法は、線の間隔をなるべく均等にすることだそうですので、試してみてください。脳には、線と線の間が統一されていると美しいと感じる感覚野があるとのことです。
箸の持ち方もペンと共通していると思います。ペンの持ち方が悪い─つまり合理的でない握り方する人は同様に箸も上手に操れないのではないでしょうか。しかし、理屈がわかっても実践できないのは、テニスや合唱と同じです。もっぱらワープロに頼る毎日です。