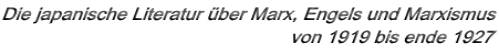
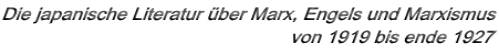
| 著者名 | 原著者 | 論文、書名 | 副題 | 収載誌名 | 巻号 | 出版社 | 発行年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルクスの経済学説 | |||||||
| 赤松要 | マルクス『経済学批判』ニ於ケル商品論(其一) | 国民経済雑誌 | 28巻5号 | 1920 | |||
| 赤松要 | マルクス『経済学批判』ニ於ケル商品論(其二) | 国民経済雑誌 | 28巻6号 | 1920 | |||
| 赤松要 | マルクスの価値法則と平均利潤率との『矛盾』 | 小泉教授及河上博士の論評の論評 | 商業経済論叢 | 創刊号 | 1923 | ||
| 赤松要 | マルクスの価値法則と生産価格 | 商学研究 | 1巻1号 | 1921 | |||
| 田中九一 | Borchardt,Julian | マルクス経済学大綱 | 社会思想叢書 | 1編 | 弘文堂 | 1925 | |
| 西雅雄 | 「マルクス経済学大綱」を読む | マルクス主義 | 3巻1号 | 1925 | |||
| 伊藤藤次郎 | ユリアン・ボルハルト | 我等 | 6巻9号 | 1924 | |||
| 友岡久雄 | ニコライ・ブハリン | 帝国主義と資本の蓄積 | 社会思想叢書 | 9編 | 同人社書店 | 1927 | |
| 稲垣守克 | ニコライ・ブハリン | 転換期の経済学 | 改造社 | 1923 | |||
| 佐野文夫 | ブハリン | 転形期経済学 | 同人社書店 | 1928 | |||
| 森戸辰男 | Cunow,Heinrich | マルクスの『剰余価値学説史』と階級闘争 | 大原社会問題研究所雑誌 | 3巻2号 | 1925 | ||
| 細野三千雄 | Dietzgen,E. | デイーツゲンの『資本論』評 | 社会思想 | 2巻3号 | 1923 | ||
| 鳥海篤助 | Dwojlazki | ローザ資本蓄積論の批評 | 社会科学 | 3巻2号 | 1927 | ||
| 赤松五百麿 | W.H.エメット | マルクス説における『價値』および『交換價値』なる術語について | 我等 | 8巻2号 | 1926 | ||
| 藤井米三 | 賃労働について | 社会科学 | 3巻4号 | 1927 | |||
| 福田徳三 | アリストテレースの『流通の正義』=マルクスの其解釈に関する疑(其一) | 附 河上博士等訳資本論中或重要なる不正確又は誤謬について | 改造 | 9巻12号 | 1927 | ||
| 福本和夫 | 経済学批判の方法論 | 白揚社 | 1926 | ||||
| 古屋美貞 | 社会主義の利子掠奪説の批判的研究 | 同志社論叢 | 13号 | 1924 | |||
| 二葉大三 | 労働価値説の一弁護 | 小泉教授の「マルクスの價値学説に對する一批評」を難じ高畠氏の批評に及ぶ | 我等 | 5巻3号 | 1923 | ||
| 長谷田泰三 | マルクスのアダムスミス價値学説批評 | 経済学論集 | 1巻2号 | 1922 | |||
| 樋口麗陽 | 誰にもわかるマルクス資本論 | 日本書院 | 1919 | ||||
| 土方成美 | マルクス価値論の排撃 | 日本評論社 | 1927 | ||||
| 土方成美 | マルクス價値論を排撃す | 経済研究 | 4巻3号 | 1927 | |||
| 土方成美 | マルクスに對する無理解とは何か | 経済研究 | 4巻4号 | 1927 | |||
| 林要 | ヒルファディング、ルードルフ | 貨幣と信用 | 金融資本論 | 1分冊 | 弘文堂書房 | 1926 | |
| 林要 | ヒルファディング、ルードルフ | 資本の動員と金融資本の独裁 | 金融資本論 | 2分冊 | 弘文堂書房 | 1926 | |
| 林要 | ヒルファディング、ルードルフ | 恐慌と帝国主義 | 金融資本論 | 3分冊 | 弘文堂書房 | 1927 | |
| 久留間鮫造 | ヒルファディング、ルードルフ | 貨幣の必然性 | 大原社会問題研究所雑誌 | 2巻1号 | 1924 | ||
| 赤松五百麿 | ヒルファーディング、ルードルフ | フランツ・ペトリー著『マルクス価値論の社会的内容』を評す | 我等 | 7巻12号 | 1925 | ||
| 赤松五百麿 | ヒルファーディング、ルドルフ | ボエーム・バウエルクのマルクス評 | 我等 | 7巻4号 | 1925 | ||
| 赤松五百麿 | ヒルファーディング、ルドルフ | ボエーム・バウエルクのマルクス評(続) | 我等 | 7巻5号 | 1925 | ||
| 赤松五百麿 | ヒルファーディング、ルドルフ | ボエーム・バウエルクのマルクス評(三) | 我等 | 7巻6号 | 1925 | ||
| 赤松五百麿 | ヒルファーディング、ルドルフ | ボエーム・バウエルクのマルクス評(四) | 我等 | 7巻7号 | 1925 | ||
| 赤松五百麿 | ヒルファーディング、ルドルフ | ボエーム・バウエルクのマルクス評(五) | 我等 | 7巻8号 | 1925 | ||
| 赤松五百麿 | ヒルファーディング、ルドルフ | ボエーム・バウエルクのマルクス評(六) | 我等 | 7巻9号 | 1925 | ||
| 堀経夫 | 価値論上のリカアドとマルクス(一) | 経済論叢 | 11巻4号 | 1920 | |||
| 堀経夫 | 価値論上のリカアドとマルクス(二) | 経済論叢 | 11巻5号 | 1920 | |||
| 堀経夫 | 価値論上のリカアドとマルクス(三・完) | 経済論叢 | 11巻6号 | 1920 | |||
| 堀経夫 | マルクス労働価値論の根本命題に就いて(一) | 経済論叢 | 11巻2号 | 1920 | |||
| 堀経夫 | マルクス労働価値論の根本命題に就いて(二・完) | 経済論叢 | 11巻3号 | 1920 | |||
| 上原好咲 | ハインドマン,H.M. | 社会主義経済学 | 内外出版 | 1924 | |||
| 猪俣津南雄 | 金融資本論 | 希望閣 | 1925 | ||||
| 猪俣津南雄 | マルクス『経済学批判』 | 社会問題講座 | 8巻 | 新潮社 | 1926 | ||
| 猪俣津南雄 | 資本主義崩壊の理論的論拠 | 改造 | 8巻1号 | 1926 | |||
| 猪俣津南雄 | 帝国主義の理論と没落の過程 | 社会科学 | 3巻2号 | 1927 | |||
| 加田哲二 | マルクスの價値論と河上博士の解釈 | 解放 | 5巻4号 | 1923 | |||
| 小栗慶太郎 | ヘルマン・カーン | マルクス資本論の展開 | マルクス思想叢書 | 4編 | 新潮社 | 1926 | |
| 高畠素之 | カウツキー、カール | マルクス資本論解説 | 売文社出版部 | 1919 | |||
| 高畠素之 | カウツキー、カール | 改訂 資本論解説 | 而立社 | 1924 | |||
| 高畠素之 | カウツキー、カール | 改訳 資本論解説 | 改造社 | 1927 | |||
| 石川準十郎 | カウツキー、カール | マルクス経済学入門 | 社会哲学新学説大系 | 9巻 | 新潮社 | 1925 | |
| 久留間鮫造 | カール・カウツキー | マルクスの経済学説を克服する唯一の方法 | 大原社会問題研究所雑誌 | 2巻2号 | 1924 | ||
| 赤松五百麿 | カウツキー、カール | マルクス資本論第二巻略解 | 我等 | 8巻3号 | 1926 | ||
| 赤松五百麿 | カウツキー、カール | マルクス資本論第二巻略解(二) | 我等 | 8巻4号 | 1926 | ||
| 河上肇 | 改版 社会問題管見 | 弘文堂書房 | 1920 | ||||
| 河上肇 | 人口問題批判 | 叢文閣 | 1927 | ||||
| 河上肇 | 福田博士の『資本増殖の理法』を評す(其の一) | 社会問題研究 | 31冊 | 1922 | |||
| 河上肇 | 福田博士の『資本増殖の理法』を評す(其の二) | 社会問題研究 | 32冊 | 1922 | |||
| 河上肇 | 資本複生産に関するマルクスの表式 | 福田博士の『資本増殖の理法』を評す――其の三 | 社会問題研究 | 33冊 | 1922 | ||
| 河上肇 | 資本主義的生産の必然的行き詰まりの理法 | 福田博士の『資本増殖の理法』を評す――その四 | 社会問題研究 | 34冊 | 1922 | ||
| 河上肇 | 剰余価格論につき高田博士に答ふ | 社会問題研究 | 43冊 | 1923 | |||
| 河上肇 | 価値論断片 | 我等 | 7巻1号 | 1925 | |||
| 河上肇 | 加田教授に答ふ | マルクスの価値論について | 社会問題研究 | 45冊 | 1923 | ||
| 河上肇 | マルクスの比例的関係の鉄則 | 経済論叢 | 14巻5号 | 1922 | |||
| 河上肇 | マルクスの価値概念に関する一考察 | 櫛田民蔵氏の同題の論文を読みて | 社会問題研究 | 59冊 | 1925 | ||
| 河上肇 | マルクスの価値論に対する小泉教授の批評の批評 | 社会問題研究 | 62冊 | 1925 | |||
| 河上肇 | マルクスの労働価値説(1) | 小泉教授の之に対する批評について | 社会問題研究 | 39冊 | 1922 | ||
| 河上肇 | マルクスの労働価値説(2) | その論証法の当否(その二)=小泉教授の批評の批評 | 社会問題研究 | 40冊 | 1922 | ||
| 河上肇 | マルクスの労働価値説(3) | 社会問題研究 | 41冊 | 1922 | |||
| 河上肇 | マルクス説における資本の起源 | 経済論叢 | 18巻2号 | 1924 | |||
| 河上肇 | 『マルクス資本論解説』(新刊紹介) | 社会問題研究 | 7冊 | 1919 | |||
| 河上肇 | 労働の生産力の発展と資本蓄積との衝突――ローザ・ルクセンブルクの『資本蓄積』について | ローザ・ルクセンブルグの『資本の蓄積』について | 社会問題研究 | 69冊 | 1925 | ||
| 河上肇 | 生産政策としての社会主義 | 生産力の発展の為にマルクスの社会主義は主張せらる | 経済論叢 | 8巻1号 | 1919 | ||
| 河上肇 | 資本の社会的性質 | 経済論叢 | 20巻1号 | 1925 | |||
| 河上肇 | 資本集積の必然的傾向 | 社会問題研究 | 36冊 | 1922 | |||
| 河上肇 | 資本論第1版と第2版との相違 | 経済論叢 | 21巻3号 | 1925 | |||
| 河上肇 | 資本論劈頭の文句とマルクスの価値法則【その一】 | 櫛田民蔵氏の同題の論文について | 社会問題研究 | 63冊 | 1925 | ||
| 河上肇 | 資本論劈頭の文句とマルクスの価値法則【その二】 | 櫛田民蔵氏の同題の論文について | 社会問題研究 | 64冊 | 1925 | ||
| 河上肇 | 資本論初版の付録『価値形態』 | 我等 | 7巻10号 | 1925 | |||
| 河上肇 | 資本主義的生産組織の真相、その下に於ける生産力の分配、之に含まるゝ矛盾の増進 | 社会問題研究 | 30冊 | 1922 | |||
| 河上肇 | 高田博士の再論について | 社会問題研究 | 47冊 | 1923 | |||
| 喜多壮一郎 | スミスとマルクスの経済学説 | 二大経済学者の片鱗 | 解放 | 3巻11号 | 1921 | ||
| 北原龍雄 | 資本主義社会に於ける搾取関係の錯綜 | 赤旗[『前衛』『社会主義研究』『無産階級』合同 編者] | 3巻4号 | 1923 | |||
| 北浦千太郎 | 地代論解説 | 社会科学 | 3巻4号 | 1927 | |||
| 小林丑三郎 | 餘剰價値の研究 | 経済及商業 | 4巻1号 | 1925 | |||
| 小泉信三 | 価値論と社会主義 | 改造社 | 1923 | ||||
| 小泉信三 | Dietzel, H. | 「価値論の価値」 | 三田学会雑誌 | 20巻3号 | 1926 | ||
| 小泉信三 | 英国に於けるマルクス價値論々争 | 改造 | 7巻11号 | 1925 | |||
| 小泉信三 | 地代論に於けるマルクスとロオドベルトス | 三田学会雑誌 | 16巻12号 | 1922 | |||
| 小泉信三 | マルクスの価値論と価格論 | 解放 | 2巻1号 | 1920 | |||
| 小泉信三 | 三度び労働費用と平均利潤の問題を論ず | 改造 | 7巻4号 | 1925 | |||
| 小泉信三 | 四度び労働費用と平均利潤の問題を論ず | 河上肇櫛田民蔵両氏のマルクス辯護説 | 改造 | 7巻11号 | 1925 | ||
| 小泉信三 | 櫛田氏に答ふ | 改造 | 8巻5号 | 1926 | |||
| 小泉信三 | 生産費説と労働価値説 | 解放 | 4巻11号 | 1922 | |||
| 赤松五百麿 | クチンスキー,ユルゲン | 資本蓄積の弁証法的発展 | 商学論叢 | 1巻3号 | 1926 | ||
| 櫛田民蔵 | 福本氏著『経済学批判の方法論』に就いての一感想 | 社会科学 | 2巻8号 | 1926 | |||
| 櫛田民蔵 | 学説の矛盾と事実の矛盾 | 小泉信三氏のマルクス評 | 改造 | 7巻6号 | 1925 | ||
| 櫛田民蔵 | 價値法則に関する小泉教授の『答弁』 | 我等 | 9巻2号 | 1927 | |||
| 櫛田民蔵 | カール・マルクスを克服する者 | マルクスの價値法則と労働の生産力との関係 再び小泉信三氏の『マルクス評』を評す | 改造 | 8巻4号 | 1926 | ||
| 櫛田民蔵 | マルクス価値概念に関する一考察 | 河上博士の『価値人類犠牲説』に対する若干の疑問 | 大原社会問題研究所雑誌 | 3巻1号 | 1925 | ||
| 櫛田民蔵 | マルクス価値論中誤解し易き一句に就いて | 二月三日東京社会科学研究会有志の読書会席上にて述べたる所感の一端 | 我等 | 7巻2号 | 1925 | ||
| 櫛田民蔵 | マルクスの価値法則と平均利潤 | 河上教授の批評(『社会問題研究』第六十三冊及び六十四冊)に答ふ | 大原社会問題研究所雑誌 | 5巻1号 | 1927 | ||
| 櫛田民蔵 | マルクス價値論の排撃 | 土方成美君の『排撃』を読む | 我等 | 9巻8号 | 1927 | ||
| 櫛田民蔵 | 資本論劈頭の文句とマルクスの価値法則 | 我等 | 7巻6号 | 1925 | |||
| 櫛田民蔵 | 商品価値の批判序説 | マルクスの価値法則概要 | 社会問題講座 | 13巻 | 新潮社 | 1926 | |
| 福田徳三 | リープクネヒト,カール | リーブクネヒト獄中遺稿 マルクス価値論批評(其の一) | 改造 | 5巻3号 | 1923 | ||
| 福田徳三 | リープクネヒト,カール | リーブクネヒト獄中遺稿 マルクス価値論批評(其の二) | 改造 | 5巻4号 | 1923 | ||
| 福田徳三 | リープクネヒト,カール | リーブクネヒト獄中遺稿 マルクス価値論批評(其の三) | 改造 | 5巻6号 | 1923 | ||
| 長谷部文雄 | リンゼイ、A.D. | マルクスの価値論 | 同志社論叢 | 22号 | 1927 | ||
| 益田豊彦、高山洋吉 | ルクセンブルク、ローザ | 資本蓄積論 | 同人社書店 | 1927 | |||
| 横田千元 | ルクセンブルク、ローザ | 資本蓄積論 第1冊、第2冊 | 白揚社 | 1926 | |||
| 宗道太 | ルクセンブルク、ローザ | 資本蓄積再論 | 亜流はマルクス説から何を作り出したか | 同人社 | 1926 | ||
| 堺利彦 | ルクセンブルク、ローザ | 資本論第二巻及び第三巻 | マルクス主義 | 1巻1号 | 1924 | ||
| 久留間鮫造 | ルクセンブルク、ローザ | アダム・スミス誕生二百年に際して | 大原社会問題研究所雑誌 | 1巻1号(第1冊) | 1923 | ||
| 島田保太郎? | メリー・マーシー | マルクス経済学入門 | 第四級民叢書 | 1編 | 三田書房 | 1919 | |
| 南亮三郎 | 人口法則と産業予備軍の法則 | 商学討究 | 1巻 | 1926 | |||
| 森耕ニ郎 | マルクスの労賃論(一) | 経済論叢 | 18巻5号 | 1924 | |||
| 森耕ニ郎 | マルクスの労賃論(二・完) | 経済論叢 | 18巻6号 | 1924 | |||
| 森戸辰男 | 『剰余価値学説史』に就いて | 大原社会問題研究所パンフレット | 19冊 | 1925 | |||
| 森戸辰男 | マルクス『剰余価値学説史』とその学界への貢献 | 我等 | 7巻4号 | 1925 | |||
| 大森義太郎 | マルクス経済学の方法論的特質について | 大衆 | 2巻1号 | 1927 | |||
| 大森義太郎 | マルクス経済学の方法論的特質について(続き) | 大衆 | 2巻2号 | 1927 | |||
| 大森義太郎 | ブハーリン限界効用學説批評 | N.Bucharin:Die politische Oekonomie des Rentners | 経済学論集 | 5巻4号 | 1927 | ||
| 大森義太郎 | まてりありすむす・みりたんす | 土方教授の『配分史観』なるものゝ克服 土方教授の唯物史観批評の反撃 | 改造 | 9巻12号 | 1927 | ||
| 大山千代雄 | ブハリンの限界利用説批評に就て | 経済研究 | 4巻4号 | 1927 | |||
| 高橋貞樹 | フィリップス・プライス | 『資本蓄積論』に就いて | ローザ・ルクセンブルグと「中央派」 | マルクス主義 | 1巻3号 | 1924 | |
| 友岡久雄 | Rubin, J. | ペートリ著「マルクス価値論の社会的内容」に就て | 社会思想 | 5巻6号 | 1926 | ||
| 坂千秋 | マルクスの使用価値 | (上) | 社会政策時報 | 30号 | 1923 | ||
| 三邊金蔵 | 資本主義崩壊必然論に對する一考察(上) | 福田、河上両博士の論争を批評す | 財政経済時報 | 10巻3号 | 1923 | ||
| 三邊金蔵 | 資本主義崩壊必然論に對する一考察(中) | 福田、河上両博士の論争を批評す | 財政経済時報 | 10巻5号 | 1923 | ||
| 三邊金蔵 | 資本主義崩壊必然論に對する一考察(下) | 福田、河上両博士の論争を批評す | 財政経済時報 | 10巻6号 | 1923 | ||
| 三邊金蔵 | マルクスの二つの價値説と平均利潤率の問題 | 三田学会雑誌 | 18巻1号 | 1924 | |||
| 三邊金蔵 | マルクスの価値論に對するBeerの批評 | 三田学会雑誌 | 18巻2号 | 1924 | |||
| 記載なし | ブハリン | 資本主義の崩壊と労働階級 | 無産階級 | 1巻3号 | 1922 | ||
| 伊藤藤次郎 | Starr, Mark | 労働者経済学 | 白揚社 | 1926 | |||
| 高畠素之 | マルクス価値説・剰余価値説及其批判 | 改造 | 1巻10号 | 秋季特別号 | 1919 | ||
| 高畠素之 | マルクス価値説の「矛盾」 | 山川均対小泉信三氏の論戦を背景にして | 解放 | 4巻10号 | 1922 | ||
| 高畠素之 | 資本論第三巻まで | 国家社会主義 | 1巻2号 | 1919 | |||
| 高畠素之 | 労働商品論 | 国家社会主義 | 1巻3号 | 1919 | |||
| 高畠素之 | カール・マルクスの地代論 | リカルド及ロドベルトス説と比較しつつ | 改造 | 8巻3号 | 1926 | ||
| 高畠素之 | マルクスの『資本論』 | 改造 | 9巻11号 | 1927 | |||
| 高畠素之 | マルクスの余剰価値説 | 実業之日本社 | 1925 | ||||
| 高畠素之、北原龍雄 | 資本論講話 | 一、序言 | 解放 | 3巻5号 | 1921 | ||
| 高畠素之、北原龍雄 | 資本論講話 | 第二回―資本蓄積の行程 | 解放 | 3巻6号 | 1921 | ||
| 高畠素之、北原龍雄 | 資本論講話 | 第三回―剰余価値の外観 | 解放 | 3巻7号 | 1921 | ||
| 高畠素之、北原龍雄 | 資本論講話 | 第四回―商品と其の価値及価格(一) | 解放 | 4巻5号 | 1922 | ||
| 高畠素之、北原龍雄 | 資本論講話 | 第五回―商品と其の価値及価格(二) | 解放 | 4巻6号 | 1922 | ||
| 高畠素之、北原龍雄 | 資本論講話 | 第六回―剰余価値と其の搾取 | 解放 | 4巻7号 | 1922 | ||
| 高畠素之、北原龍雄 | 資本論講話 | 第七回―剰余価値率と利潤率 | 解放 | 4巻8号 | 1922 | ||
| 高田保馬 | 河上博士の剰餘価格論 | 解放 | 5巻2号 | 1923 | |||
| 高田保馬 | 剰餘価格に関して | 再び教を河上博士に請ふ | 解放 | 5巻7号 | 1923 | ||
| 高田保馬 | 剰餘價格第三論 | 河上博士の再論について | 改造 | 6巻12号 | 1924 | ||
| 田島錦治 | マルクス氏余剰価値説の評論(一) | 経済論叢 | 14巻1号 | 1922 | |||
| 田島錦治 | マルクス氏余剰価値説の評論(二) | 経済論叢 | 14巻3号 | 1922 | |||
| 田島錦治 | マルクス氏余剰価値説の評論(三・完) | 経済論叢 | 14巻4号 | 1922 | |||
| 田島錦治 | マルクス氏の集産主義の実行難を論ず(一) | 経済論叢 | 15巻3号 | 1922 | |||
| 田島錦治 | マルクス氏の集産主義の実行難を論ず(二・完) | 経済論叢 | 15巻6号 | 1922 | |||
| 田島錦治 | 産業集中に就いてのマルクス説の謬想 | 経済論叢 | 20巻1号 | 1925 | |||
| 淡徳三郎 | 人口論 | 社会科学 | 3巻4号 | 1927 | |||
| 久保譲 | ダブリユー・チエルケソフ | マルクス資本集中説の誤謬 | 労働運動 | 5巻1号 | 1926 | ||
| 久保譲 | ダブリユー・チエルケソフ | マルクス資本集中説の誤謬(二) | 労働運動 | 5巻2号 | 1926 | ||
| 久保譲 | ダブリユー・チエルケソフ | マルクス資本集中説の誤謬(三) | 労働運動 | 5巻3号 | 1926 | ||
| 久保譲 | ダブリユー・チエルケソフ | マルクス資本集中説の誤謬(四) | 労働運動 | 5巻5号 | 1926 | ||
| 久保譲 | ダブリユー・チエルケソフ | マルクス資本集中説の誤謬(五) | 労働運動 | 5巻6号 | 1926 | ||
| 友岡久雄 | ヒルファーディングの『恐慌の原因』 | 経済研究 | 2巻1号 | 1925 | |||
| 八木芳之助 | マルクスの絶對地代に就いて(一) | 経済論叢 | 20巻5号 | 1925 | |||
| 八木芳之助 | マルクスの絶對地代に就いて(二) | 経済論叢 | 20巻6号 | 1925 | |||
| 八木芳之助 | マルクスの絶対地代と価値法則 | 「マルクスの絶對地代に就いて」其三・完 | 経済論叢 | 21巻1号 | 1925 | ||
| 山口正太郎 | マルクスの余剰価値構成の原理に就いて | 同志社論叢 | 3号 | 1920 | |||
| 山口正太郎 | 社会価値としての経済価値 | 解放 | 5巻3号 | 1923 | |||
| 山川均 | マルクス資本論大綱 | [再版の刊行年とした 編者] | 三田書房 | 1919 | |||
| 山川均 | マルクスの価値及び剰余価値学説 | 東方時論 | 5巻9号 | 1920 | |||
| 山本勝市 | 機械と労賃との総合関係についてのマルクスの見解 | 経済論叢 | 19巻4号 | 1924 | |||
| 安田仁 | マルキシストの見たる通貨恐慌 | 金子直吉氏の不景気原因説を評す | 潮流 | 1巻1号 | 1924 | ||
| 安田与四郎 | マルクス価値論排撃に就て | 土方博士に問ふ | ダイヤモンド | 15巻29号 | 1927 | ||
| 吉岡淡水 | マルクスの資本論 | 最新学芸叢書 | 8編 | 学芸書院 | 1919 | ||
| マルクス主義の国家論 | |||||||
| 森戸辰男 | Adler, Max | マルキシズムにおける国家と強制秩序 | マックス・アードラアを紹介す | 我等 | 8巻3号 | 1926 | |
| 河上肇 | Borchardt, Julian | 社会主義の未来国(一) | 社会問題研究 | 21冊 | 1921 | ||
| 河上肇 | Borchardt, Julian | 社会主義の未来国(二) | 社会問題研究 | 22冊 | 1921 | ||
| 遠藤友四郎(無水) | 『国家』に躓く人々とエンゲルス説 | 国家社会主義 | 1巻3号 | 1919 | |||
| 福田徳三 | ボルシェヴヰズム研究 | 改造社 | 1922 | ||||
| 波多野鼎 | 共産党宣言の国家論 | 社会思想 | 2巻8号 | 1923 | |||
| 波多野鼎 | マルクス主義における国家の観念 | 特にエンゲルスの国家観念 | 社会思想 | 4巻7号 | 1925 | ||
| 岩城忠一 | 福田博士の『レーニンの国家理論』とケルゼンの『社会主義と国家』との奇蹟的合致 | 商学論叢 | 1巻1号 | 1926 | |||
| 加田忠臣 | マルクス派の国家観(一) | 三田学会雑誌 | 14巻7号 | 1920 | |||
| 加田忠臣 | マルクス派の国家観(二) | 三田学会雑誌 | 14巻8号 | 1920 | |||
| 加田忠臣 | マルクス派の国家観(三、完) | 三田学会雑誌 | 14巻9号 | 1920 | |||
| 勝原雅大 | マルキシズムの国家理論 | 社会科学研究叢書 | 1篇 | 国際思潮研究会 | 1926 | ||
| 高畠素之 | カール・カウツキー | 階級独裁と政党独裁 | 解放 | 4巻3号 | 1922 | ||
| [記載なし] | カール・カウツキー | マルクスの国家観 | 社会科学 | 2巻6号 | 1926 | ||
| 河上肇 | 一八七五年に書いたマルクスの手紙 | マルクスの理想及び其の実現の過程 | 社会問題研究 | 27冊 | 1921 | ||
| 河上肇 | 時期尚早なる社会革命の企について | 経済論叢 | 15巻4号 | 1922 | |||
| 河上肇 | マルクス説における社会的革命と政治的革命 | 社会問題研究 | 37号 | 1922 | |||
| 河上肇 | 露西亜革命と社会主義革命 | 露西亜革命に関する若干の理論的考察 | 社会問題研究 | 29冊 | 1922 | ||
| 河上肇 | マルクス主義に謂ふ所の過渡期について | 経済論叢 | 13巻6号 | 1921 | |||
| 小泉信三 | 改訂 社会問題研究 | 岩波書店 | 1925 | ||||
| 小泉信三 | 社会主義と国家(一) | 三田学会雑誌 | 17巻2号 | 1923 | |||
| 小泉信三 | 社会主義と国家(二) | 三田学会雑誌 | 17巻3号 | 1923 | |||
| 小泉信三 | 社会主義と国家(三) | 三田学会雑誌 | 17巻4号 | 1923 | |||
| 小泉信三 | 社会主義と国家(四、完) | 三田学会雑誌 | 17巻5号 | 1923 | |||
| 河野密 | 階級国家の崩壊過程 | 我等 | 7巻11号 | 1925 | |||
| 河野密 | マルクスの国家論 | 社会問題講座 | 8巻 | 新潮社 | 1926 | ||
| 河野密 | マルクスの国家論 | 社会問題講座 | 10巻 | 新潮社 | 1926 | ||
| 河野密 | マルクスの国家論 | 社会問題講座 | 11巻 | 新潮社 | 1926 | ||
| 河野密 | マルクス説に於ける社会と国家 | 我等 | 8巻1号 | 1926 | |||
| 森戸辰男 | マルクス国家観の生誕 | 大原社会問題研究所雑誌 | 4巻1号 | 1926 | |||
| 森戸辰男 | スチルナアの無政府主義とマルクスの国家観 | 大原社会問題研究所雑誌 | 5巻1号 | 1927 | |||
| 佐野学 | 社会主義「未来国家」を論ず | 自治は自由の最大の表現である | 解放 | 2巻3号 | 1920 | ||
| 高橋貞樹 | 国家に関する一断片 | マルクス主義 | 1巻5号 | 1924 | |||
| 高畠素之 | マルキシズムと国家主義 | 改造社 | 1927 | ||||
| 山口氏門 | 福田博士の階級支配理論 | 『共産党宣言』によるプロレタリア国家の性質 | 無産階級 | 1巻4号 | 1922 | ||
| マルクスの著作 | |||||||
| *全集 | |||||||
| *『資本論』 | |||||||
| *個別論文 | |||||||
| 服部英太郎 | マルクス | デモクリットとエピクールとの自然哲学の差異 | カール・マルクス学位論文 | 社会思想 | 6巻9号 | 1927 | |
| 服部英太郎 | マルクス | デモクリットとエピクールとの自然哲学の差異(二) | カール・マルクス学位論文 | 社会思想 | 6巻10号 | 1927 | |
| 細川嘉六・久留間鮫造 | マルクス | 猶太人問題を論ず | 同人社 | 1925 | |||
| 安倍浩 | マルクス | 猶太人問題 | 『巴里コムミューン』所収 | 而立社 | 1924 | ||
| 河野密 | マルクス・エンゲルス | 神聖家族 | マルクス全集 | 11冊 | 大鐙閣 | 1923 | |
| 経済学批判会 | マルクス・エンゲルス | 思弁的構成の秘密(1844年、マルクス) | マルキシズム叢書第10冊 原文対訳 唯物弁証法(マルクス・エンゲルス・およびレーニンの諸著作よりの抜粋) | 1927 | |||
| 佐野文夫 | マルクス | フォイエルバッハ論綱 [『フォイエルバッハ論』所収] | 同人社書店 | 1925 | |||
| 河上肇 | マルクス | フォイエルバッハに関するテーゼ(マルクス遺著) | 社会問題研究 | 71冊 | 1926 | ||
| 石川準十郎 | マルクス | マルキシズムの根柢 | マルクス思想叢書 | 1 | 新潮社 | 1927 | |
| 森戸辰男 | マルクス・エンゲルス | 『唯一者』の結構 | 『聖マツクス』よりの断章 | 大原社会問題研究所雑誌 | 5巻1号 | 1927 | |
| 櫛田民蔵・森戸辰男 | マルクス・エンゲルス | 『独逸的観念形態』の第一篇 | マルクス,エンゲルス遺稿 フオイエルバツハ論 | 我等 | 8巻5号 | 1926 | |
| 櫛田民蔵・森戸辰男 | マルクス・エンゲルス | 『独逸的観念形態』の第一篇(二,完) | マルクス,エンゲルス遺稿 フオイエルバツハ論 | 我等 | 8巻6号 | 1926 | |
| 経済学批判会 | マルクス・エンゲルス | 唯物的および観念的見解の対立(1845年、マルクス、エンゲルス) | マルキシズム叢書第10冊 原文対訳 唯物弁証法(マルクス・エンゲルス・およびレーニンの諸著作よりの抜粋) | 1927 | |||
| 西雅雄 | 『哲学の貧困』の翻訳に就いて | マルクス主義 | 4巻6号 | 1926 | |||
| 淺野研眞 | マルクス | 哲学の貧困 | プルードン氏の『貧困の哲学』への一答弁 | 社会批判パンフレット | No.5 | 社会批判社 | 1923 |
| 経済学批判会 | マルクス | 経済学の形而上学(1847年、マルクス) | マルキシズム叢書第10冊 原文対訳 唯物弁証法(マルクス・エンゲルス・およびレーニンの諸著作よりの抜粋) | 1927 | |||
| 幸徳秋水・堺利彦 | マルクス・エンゲルス | 共産党宣言 | 羅府 日本人労働協会 | 1926 | |||
| 河上肇 | マルクス,カアル | 賃労働と資本 労賃、価格及び利潤 | 弘文堂書房 | 1921 | |||
| 福田徳三 | マルクスの真本と河上博士の原本 | 解放 | 1巻1号 | 1919 | |||
| 河上肇 | 改訳『賃労働と資本』を公にするに際し福田博士に答ふ | 社会問題研究 | 28冊 | 1921 | |||
| 堺利彦 | マルクス | 労働と資本 | 無産社パンフレット | 2 | 無産社 | 1922 | |
| 田中九一 | マルクス | ブルジヨア革命の社会的基礎 | 社会思想 | 3巻4号 | 1924 | ||
| 大内兵衛 | マルクス | 税制改革論批判 | Emile de Girardin, Le socialisme et l'impôt. Paris. 1850. 論評 | 大原社会問題研究所雑誌 | 4巻1号 | 1926 | |
| 中川善之助 | マルクス | 呉越の弁 | 一八四九年四月八日ケルンの陪審法廷に於ける弁論 | 社会科学 | 2巻8号 | 1926 | |
| 大内兵衛 | マルクス | イギリスの選挙-トーリー党とホイッグ党 | 『イギリス通信』その一 | 我等 | 8巻9号 | 1926 | |
| 大内兵衛 | マルクス | チャーティスト | 『イギリス通信』その二 | 我等 | 8巻10号 | 1926 | |
| 大内兵衛 | マルクス | 選挙腐敗 | 『イギリス通信』その三 | 我等 | 8巻11号 | 1926 | |
| 大内兵衛 | マルクス | 選挙の結果 | 『ロンドン通信』その四 | 我等 | 8巻12号 | 1926 | |
| 大内兵衛 | マルクス | 貧窮と自由貿易-商業恐慌来らんとす | 『イギリス通信』その五 | 我等 | 9巻1号 | 1927 | |
| 大内兵衛 | マルクス | 景気発作期の政治現象 | 『イギリス通信』その六 | 我等 | 9巻2号 | 1927 | |
| 大内兵衛 | マルクス | 議会-自由貿易に関する決議-ディスレリーの予算案 | 『ロンドン通信』その九 | 我等 | 9巻4号 | 1927 | |
| 大内兵衛 | マルクス | 内閣の敗北 | 『ロンドン通信』その一〇 | 我等 | 9巻5号 | 1927 | |
| 大内兵衛 | マルクス | 老耄れ政府-連立内閣の前途 | 『ロンドン通信』その一一 | 我等 | 9巻7号 | 1927 | |
| 大内兵衛 | マルクス | スザーランド女公と奴隷 | 『イギリス通信』その一三 | 我等 | 9巻8号 | 1927 | |
| 小林良正 | マルクス | マルクスの支那印度論 | 嚴松堂 | 1927 | |||
| 嘉治隆一 | マルクス | 支那とヨーロッパとに於ける革命 | 我等 | 8巻2号 | 1926 | ||
| 宮川実 | マルクス | 経済学批判 | 叢文閣 | 1926 | |||
| 河上肇・宮川実 | マルクス | 経済学批判序説 | マルキシズム叢書 | 6冊 | 弘文堂 | 1927 | |
| 経済学批判会 | マルクス | 経済学研究の一般的結論(1859年、マルクス) | マルキシズム叢書第10冊 原文対訳 唯物弁証法(マルクス・エンゲルス・およびレーニンの諸著作よりの抜粋) | 1927 | |||
| 早野三郎 | マルクス | 労働者諸君に | 土曜会パンフレット | 1冊 | 思想社 | 1927 | |
| 松浦要 | マルクス | マルクス経済学説要旨 | 価値、価格及び利潤 | 経済社 | 1919 | ||
| 堺利彦 | マルクス | 利潤の出処 | 無産社パンフレット | 4 | 無産社 | 1923 | |
| 安倍浩 | マルクス | 賃金,価格及び利潤 | 第7篇カール・マルクス | 経済学説体系 | 1巻 | 而立社 | 1924 |
| [記載なし] | マルクス | フランスに於ける内乱 | 共産主義研究 | 2冊 | 1924 | ||
| 境顯平 | マルクス | 普仏戦争に関するインターナショナル総務会の宣言 | 共産主義研究 | 1冊 | 1924 | ||
| 境顯平 | マルクス | 普仏戦争に関するインターナショナル総務会の第二宣言 | 共産主義研究 | 3冊 | 1924 | ||
| 水谷長三郎 | マルクス | ゴータ綱領批判 | 内外出版 | 1924 | |||
| 水谷長三郎 | マルクス | 改訂 ゴータ綱領批判 | マルキシズム叢書 | 12冊 | 弘文堂 | 1927 | |
| 堺利彦 | マルクス | ゴタ綱領批評 | 無産社パンフレット | 6 | 無産社 | 1925 | |
| エンゲルスの著作 | |||||||
| 後藤信夫・嘉治隆一 | フリイドリッヒ・エンゲルス | 経済学批判大綱 | 我等 | 6巻8号 | 1924 | ||
| 嘉治隆一 | エンゲルス | カーライル批判(上) | 我等 | 7巻2号 | 1925 | ||
| 嘉治隆一 | エンゲルス | カーライル批判(中) | 我等 | 7巻3号 | 1925 | ||
| 竹内謙二 | エンゲルス | 英国労働階級の状態 | 同人社書店 | 1926 | |||
| [記載なし] | エンゲルス | 無産階級の過去、現在及未来 | 社会思想社 | 1922 | |||
| 鈴木厚 | フレデリツク・エンゲルス | 共産主義の初歩(一) | エンゲルスの「共産党宣言」の下書 | 進め | 3巻12号 | 1925 | |
| 西雅雄 | エンゲルス | ドイツ農民戦争 | マルクス‐エンゲルス政治論叢書 | 希望閣 | 1927 | ||
| 経済学批判会 | エンゲルス | マルクスの『経済学批判』について(1859年、エンゲルス) | マルキシズム叢書第10冊 原文対訳 唯物弁証法(マルクス・エンゲルス・およびレーニンの諸著作よりの抜粋) | 1927 | |||
| 安倍浩 | エンゲルス | 巴里コムミューン 独逸語版に對する緒言 | 『巴里コムミューン』所収 | 而立社 | 1924 | ||
| 服部之総 | エンゲルス | エンゲルス「権威の原理について」 | 我等 | 9巻8号 | 1927 | ||
| 岡田宗司? | エンゲルス | バクーニン主義者の活動 | 叢文閣 | 1927 | |||
| 嘉治隆一 | エンゲルス | ロシアに於ける資本主義の発達(前書、本文、後書) | 近代ロシア社會史研究 / 嘉治隆一著 所収 | 同人社 | 1925 | ||
| 河野密・林要 | エンゲルス | 反デューリング論 | マルキシズム叢書 | 8冊 | 弘文堂書房 | 1927 | |
| 平野義太郎 | エンゲルス | 永遠の真理・自由・平等の批判 | 反デューリング論中の「道徳と法律」 | 同人社 | 1927 | ||
| 経済学批判会 | エンゲルス | 唯物弁証法とマルキシズム(1877年、エンゲルス) | マルキシズム叢書第10冊 原文対訳 唯物弁証法(マルクス・エンゲルス・およびレーニンの諸著作よりの抜粋) | 1927 | |||
| 河上肇 | エンゲルス | 科学的社会主義と唯物史観 | 社会問題研究 | 17冊 | 1920 | ||
| [記載なし] | エンゲルス | 資本と剰余価値 | 無産階級 | 1巻1号 | 1922 | ||
| 服部之総 | エンゲルス | 『強力説』批判 | 我等 | 8巻7号 | 1926 | ||
| 服部之総 | エンゲルス | 『強力説』批判[連続論文だが番号が振られていない 編者] | 我等 | 8巻8号 | 1926 | ||
| 服部之総 | エンゲルス | 『強力説』批判(結び) | 我等 | 8巻9号 | 1926 | ||
| 堺利彦 | エンゲルス | 空想的及科学的社会主義 | 大鐙閣 | 1921 | |||
| 遠藤友四郎 | エンゲルス | 科学的社会主義 | 附録 カウツキー著 エンゲルス伝 | 文泉堂 | 1920 | ||
| 堺利彦 | エンゲルス | 空想から科学へ | 空想的及科学的社会主義 | 白揚社 | 1924 | ||
| 小泉信三 | エンゲルス | エンゲルスのロオドベルトス批評(一) | 三田学会雑誌 | 16巻10号 | 1922 | ||
| 小泉信三 | エンゲルス | エンゲルスのロオドベルトス批評(二、完) | 三田学会雑誌 | 16巻11号 | 1922 | ||
| 内藤吉之助 | エンゲルス | 家族・私有財産及び国家の起源 | リユイス・エチ・モルガンの研究に因みて | 有斐閣 | 1922 | ||
| 西雅雄 | エンゲルス | 家族、私有財産及び国家の起源 | リュウィス・エッチ・モルガンの研究に因みて | 白揚社 | 1927 | ||
| 堺利彦 | エンゲルス | 氏族制と国家 | 新社会評論 | 7巻2号 | 1920 | ||
| 佐野文夫 | フリードリッヒ・エンゲルス,カール・マルクス | フォイエルバッハ論 | 同人社書店 | 1925 | |||
| 石川準十郎 | エンゲルス | フォイエルバッハ論 | 『マルキシズムの根底』第2篇 | 新潮社 | 1927 | ||
| 吉山道三 | エンゲルス | 史的唯物論に就て | 共生閣 | 1927 | |||
| [記載なし] | フリードリヒ・エンゲルス | 議会と大衆運動 | マルクス主義 | 1巻2号 | 1924 | ||
| 黒田房雄 | エンゲルス | 猿の人間化に於ける労働の寄与 | 叢文閣 | 1927 | |||
| マルクスおよびエンゲルスの書簡 | |||||||
| 久留間鮫造 | マルクス | マルクスの一書簡 | 我等 | 7巻5号 | 1925 | ||
| 林房雄 | マルクス | 改版 クーゲルマンへの手紙 | 希望閣 | 1926 | |||
| [記載なし] | マルクス | 労働価値説について関する一書簡 | マルクス主義 | 2巻3号 | 1925 | ||
| 経済学批判会 | マルクス | 1868年7月10日づけの手紙 | マルキシズム叢書第10冊 原文対訳 唯物弁証法(マルクス・エンゲルス・およびレーニンの諸著作よりの抜粋) | 1927 | |||
| 山村喬 | マルクス | ロシア農村共産体の研究 | マルクスよりウエラ・ザスリツチへの手紙 | 同人社 | 1927 | ||
| 浅野晃 | マルクス | ロシア『農村共同態』に就いて(マルクス) | 我等 | 8巻10号 | 1926 | ||
| 久留間鮫造 | マルクス | 『経済学批判』の腹案に就いて | 一八五八年四月二日附エンゲルス宛書簡 | 大原社会問題研究所雑誌 | 4巻1号 | 1926 | |
| 西雅雄 | 『資本論』の最初の構想 | 『資本論』に関するマルクスの手紙(其の一) | マルクス主義 | 4巻1号 | 1926 | ||
| 西雅雄 | 『資本論』の最初の構想(続) | 『資本論』に関するマルクスの手紙(其の二) | マルクス主義 | 4巻2号 | 1926 | ||
| 西雅雄 | 『経済学批判』の完成 | 『資本論』に関するマルクスの手紙(其の三) | マルクス主義 | 4巻3号 | 1926 | ||
| 西雅雄 | 『経済学批判』の批判(一) | 『資本論』に関するマルクスの手紙(其の四) | マルクス主義 | 4巻5号 | 1926 | ||
| 西雅雄 | 『経済学批判』の批判(二) | 『資本論』に関するマルクスの手紙(其の五) | マルクス主義 | 5巻1号 | 1926 | ||
| 西雅雄 | 『経済学批判』の批判(三) | 『資本論』に関するマルクスの手紙(其の五) | マルクス主義 | 5巻2号 | 1926 | ||
| 宮川実 | マルクス | カール・マルクス『利潤率に関する書簡』 | 商学論叢 | 1巻4号 | 1926 | ||
| 嘉治隆一 | マルクス | マルクス夫人の手紙を | 文化の基礎 | 5巻9号 | 1925 | ||
| 森戸辰男 | エンゲルス | スティルナアの『唯一者』とエンゲルス | 我等 | 8巻4号 | 1926 | ||
| 小宮義孝・喜多野清一 | エンゲルス | 老戦友に与ふ | ベッカーへの『忘れられた手紙』 | 叢文閣 | 1927 | ||
| 細川嘉六 | エンゲルス | 社会主義と植民政策に関するエンゲルスの書簡 | 大原社会問題研究所雑誌 | 2巻1号(第2冊) | 1924 | ||
| 岡田宗司 | エンゲルス | 『資本』二巻三巻の読み方 | エンゲルスの書簡 | 我等 | 8巻11号 | 1926 | |
| マルクス/エンゲルス研究所について | |||||||
| [記載なし] | マルクス・エンゲルス研究所の事業 | マルクス主義 | 2巻5号 | 1925 | |||
| 櫛田民蔵 | マルクス・エンゲルス全集インターナショナル版の刊行 | 我等 | 8巻2号 | 1926 |